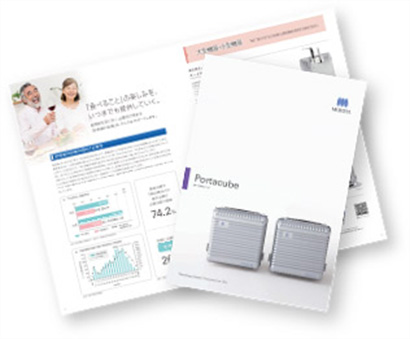はじめませんか 訪問診療
-
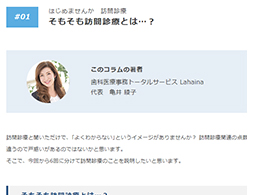 #01そもそも訪問診療とは…?訪問診療と聞いただけで、「よくわからない」というイメージがありませんか? そもそも訪問診療とはどういったものかを説明します。
#01そもそも訪問診療とは…?訪問診療と聞いただけで、「よくわからない」というイメージがありませんか? そもそも訪問診療とはどういったものかを説明します。 -
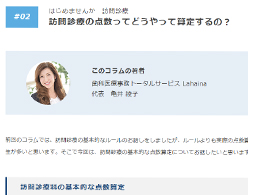 #02訪問診療の点数ってどうやって算定するの?訪問診療の基本的な点数算定や注意点加算点数について説明します。
#02訪問診療の点数ってどうやって算定するの?訪問診療の基本的な点数算定や注意点加算点数について説明します。 -
 #03訪問歯科衛生指導料の算定、どうしていますか?訪問診療の現場では欠かせない歯科衛生士。今回は訪問歯科衛生指導料を算定するためのルールについて説明します。
#03訪問歯科衛生指導料の算定、どうしていますか?訪問診療の現場では欠かせない歯科衛生士。今回は訪問歯科衛生指導料を算定するためのルールについて説明します。 -
 #04介護保険請求できていますか?請求したことがなければ少しハードルが高いように感じる、訪問診療における介護保険について解説したいと思います。
#04介護保険請求できていますか?請求したことがなければ少しハードルが高いように感じる、訪問診療における介護保険について解説したいと思います。 -
 #05訪問診療と提供文書訪問診療=文書提供というイメージがありませんか?。訪問診療と提供文書についてお話したいと思います。
#05訪問診療と提供文書訪問診療=文書提供というイメージがありませんか?。訪問診療と提供文書についてお話したいと思います。 -
 #06居宅療養管理指導(介護保険)と提供文書訪問診療に欠かせない知識となる文書提供。介護保険を利用した居宅療養管理指導を行った時に提供する文書について説明します。
#06居宅療養管理指導(介護保険)と提供文書訪問診療に欠かせない知識となる文書提供。介護保険を利用した居宅療養管理指導を行った時に提供する文書について説明します。
おうちに行こう!?訪問歯科診療のススメ?
-
 訪問歯科診療のススメ日本歯科大学教授であり、口腔リハビリテーション多摩クリニックの院長も務められる、菊谷武先生にモリタ友の会ダイレクトメールとの連動企画でコラムを執筆していただきました。
訪問歯科診療のススメ日本歯科大学教授であり、口腔リハビリテーション多摩クリニックの院長も務められる、菊谷武先生にモリタ友の会ダイレクトメールとの連動企画でコラムを執筆していただきました。
本コラムは、ひとりの患者さん(仮名 田中さん)の診療を通して、診療室で気づく口腔機能の低下、その診断法や対応法を紹介した、全6回の構成です。 -
 #01田中さーん、お入りください!咀嚼困難感を訴え、新義歯作成を希望して、78歳の男性(仮名 田中さん)が外来受診した。20年来、通ってくれている患者さんだ。メインテナンスの要請にも応え、欠かすことなく受診してくれていた。
#01田中さーん、お入りください!咀嚼困難感を訴え、新義歯作成を希望して、78歳の男性(仮名 田中さん)が外来受診した。20年来、通ってくれている患者さんだ。メインテナンスの要請にも応え、欠かすことなく受診してくれていた。 -
 #02年のせいって言えたらいいのに初回の来院時は、なぜ噛めないと患者さんが訴えるのか見当がつかなかず、「噛み合わせの調整をしました。次回まで様子を見てください」と、体よく判断を先送りしてしまった。1日の診療が終わって、ようやく落ち着いたところだ。田中さんのことが頭をよぎる。
#02年のせいって言えたらいいのに初回の来院時は、なぜ噛めないと患者さんが訴えるのか見当がつかなかず、「噛み合わせの調整をしました。次回まで様子を見てください」と、体よく判断を先送りしてしまった。1日の診療が終わって、ようやく落ち着いたところだ。田中さんのことが頭をよぎる。 -
 #03咀嚼障害は何によって起こるのかさて? 義歯もしっかりあっている田中さん、どうして噛めないのだろう。年のせいなのか?それとも・・・。いずれにしても、年のせいなんて言えない。
#03咀嚼障害は何によって起こるのかさて? 義歯もしっかりあっている田中さん、どうして噛めないのだろう。年のせいなのか?それとも・・・。いずれにしても、年のせいなんて言えない。 -
 #04「なにをみて、なにをするのか?」田中さんが来院した。前回は、「噛み合わせの調整をしました。次回まで様子を見てください」と、体よく判断を先送りにしていたので、やはり、訴えは変わっていない。それどころか、通院するのに不安があるとの発言もあった。
#04「なにをみて、なにをするのか?」田中さんが来院した。前回は、「噛み合わせの調整をしました。次回まで様子を見てください」と、体よく判断を先送りにしていたので、やはり、訴えは変わっていない。それどころか、通院するのに不安があるとの発言もあった。 -
 #05「噛めない人には噛まなくてもよい食事を」一般に運動は、「運動範囲」「運動の力」「速さ」「巧緻性」という要素に分けることができる。運動障害はこれらのいずれか、または、複数の要素が障害されることになる。咀嚼においても同様である。
#05「噛めない人には噛まなくてもよい食事を」一般に運動は、「運動範囲」「運動の力」「速さ」「巧緻性」という要素に分けることができる。運動障害はこれらのいずれか、または、複数の要素が障害されることになる。咀嚼においても同様である。 -
 #06そして、僕は在宅に向かう僕たちは、咀嚼障害は改善するものとして対応してきた。実際、多くの患者さんを直してきた。そして、多くの患者さんに感謝もされた。でも、今まで見てきた患者さんは、ある意味、特殊な患者さんだったということなのか?
#06そして、僕は在宅に向かう僕たちは、咀嚼障害は改善するものとして対応してきた。実際、多くの患者さんを直してきた。そして、多くの患者さんに感謝もされた。でも、今まで見てきた患者さんは、ある意味、特殊な患者さんだったということなのか?